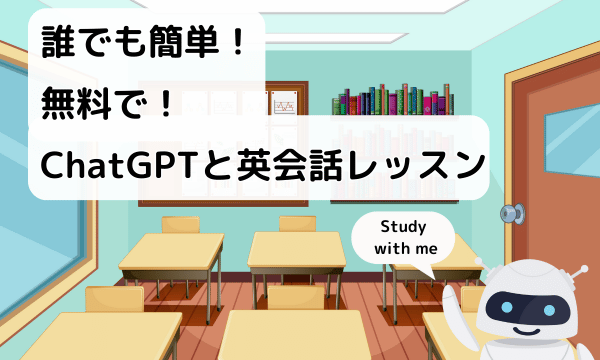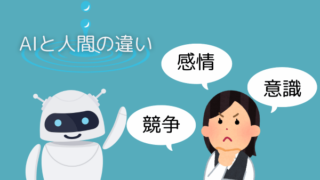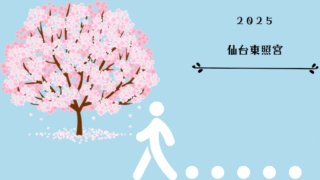※本ページは広告を含みます。
読み終えてすぐに、「ベストセラーである理由が納得できる一冊」だと感じました。
本書は、単なる話し方のテクニックではなく、話す前にどのように考えるべきかという「思考の質」を高める方法を教えてくれます。その内容は、ビジネスだけでなく日常生活にも活かせるものでした。
概要
『頭のいい人が話す前に考えていること』は、話す前の「思考の質」に焦点を当てたコミュニケーション本です。著者の安達裕哉氏は、コンサルタントとしての経験を基に、誰でも思考の質を高め、「頭のいい人」になれる方法を伝授しています。
本書では、以下のようなポイントが紹介されています:
- 「頭のよさ」は他者が決める:自分の思考が他人にどう評価されるかを意識することが重要です。
- 「知性」と「信頼」を同時に得るための7つの黄金法則:感情的な反応を避け、相手の承認欲求を満たすなど、具体的な行動指針が示されています。
- 思考を深めるための5つの思考法:客観視、整理、傾聴、質問、言語化のスキルを具体的に解説しています。
これらの内容は、AI時代においても淘汰されない、普遍的なコミュニケーションの原理原則として、多くの読者から支持を集めています。
著者紹介
安達裕哉氏は1975年生まれ。筑波大学大学院・環境科学研究科を修了後、アビームコンサルティング(旧・デロイト トーマツ コンサルティング)に入社。品質マネジメントや人事などの分野で豊富なコンサルティング経験を積み、現在はマーケティング会社「ティネクト株式会社」の代表として、企業支援、Webメディア運営、執筆活動など多方面で活躍している。
ファーストペンギンが一番偉い
本書の中で特に印象的だったのが、「ファーストペンギンが一番偉い」というエピソードです。
ある会議で若手社員が新しいアイデアを提案した際、他の社員からは批判的な意見が出ました。しかし、部門長はその意見を「非常にいい意見だった」と評価しました。
その理由を尋ねると、「最初に案を出す人は勇気が必要で、皆からバカにされないように一生懸命勉強しなければいけない。だから、最初に案を出すやつを尊重するのは仕事では当たり前です」とのことでした。
この言葉に、筆者と同じように私も目からウロコが落ちる思いでした。特に、日本社会は「出る杭は打たれる」文化が根強く、新しいものが生まれにくい土壌があると感じています。しかし、ファーストペンギンへのリスペクトが広がれば、社会はより良い方向に進んでいくと感じました。
実生活への応用
本書の最後にまとめられている「話すたびに頭が良くなるシート」は、何度も読み返したい金言が詰まっています。
たとえば「どっちの服を選んだらいい?」という日常的な問いかけへの対応エピソードからも、本書の内容が仕事だけでなく、家庭やプライベートな場面にも応用できることがよくわかります。
読んでみていただければ、ベストセラーの理由がすぐわかる一冊だと感じています。
『頭のいい人が話す前に考えていること』は、思考の質を高めることで、より良いコミュニケーションを実現するための指南書です。ビジネスシーンだけでなく、日常生活でも役立つ内容が満載ですので、ぜひ読んでみてください😊

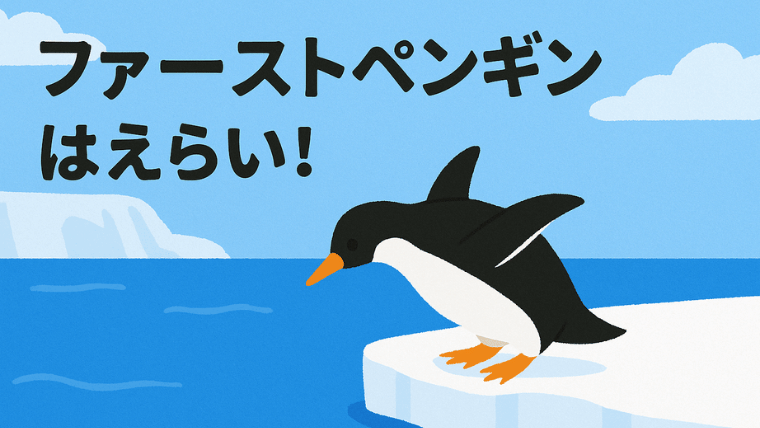
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fd8645a.18b3e735.1fd8645b.4c2d703a/?me_id=1213310&item_id=20849885&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6692%2F9784478116692_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)